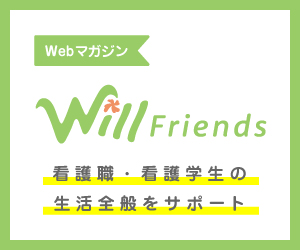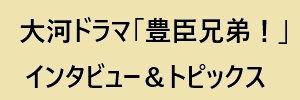エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
【インタビュー】『関ヶ原』原田眞人監督 「この映画には、映画の面白さがいっぱい詰まっています」
-岡田准一、役所広司、平岳大ら、演じた俳優たちの印象はいかがでしたか。
役所さんは同志だけど、今回は意外性のある役をやってもらうことにしました。家康は本来の彼のタイプではないけれど、岡田さんがあまりにも完璧に三成に合い過ぎているから、それに対する家康には意外性が欲しかったんです。だから僕の中ではとても楽な選択でしたが、役所さん本人はだいぶ悩んだようです。
岡田さんは最初から積極的でした。実際の三成も馬術の達人であり、官僚としてだけではなく武将としての側面もあったと思うし、そういう意味では岡田さんは完璧な三成で、僕から注文することはほとんどありませんでした。一番の冒険は島左近役の平さんでした。慣れるまでに少し時間はかかりましたが、そこを乗り切った後は、お父さん(平幹二朗)譲りの風格が出てきて、一緒にやっていて楽しかったです。
-有村架純さんはいかがでしたか。
有村さんは、原作の初芽のイメージには当てはまらないかもしれないけど、伸び盛りの個性が気に入ったので、今回はまず有村架純ありきで、彼女に合わせるような初芽に書き換えていきました。それから、関ヶ原にも関わるために、単なる間者として入り込むだけではなくて、行動できる、戦えるという女忍者にして、司馬先生が他の短編小説で描いている忍びの者のイメージを借りてきて付け加えました。だから原作とは違う初芽だけど、司馬遼太郎の世界の人物であることに変わりはないんです。
-今回は、脚本としてまとめる中で、キャラクターに対するご自分の思いを反映させた部分が多かったのでしょうか。
そうですね。司馬先生の原作を高校生の頃に読んで感銘を受けた思いを膨らませながら書いたのですが、例えば、若い頃は戦線を離脱した脱走兵のようなイメージだった三成の、理にかなわないことはしないという心情が、自分が年を取るに従って分かってきたりして…。よくよく考えると、言わなくてもいいことを言ってしまう自分によく似ているなあとか(笑)。だから、どんどんと三成が理解できるようになってきたりしました。そういう意味では自分の気持ちを入れ込みやすかったです。家康の場合は、今までいろいろと語られてはいるけれども、それとはちょっと違うものにしようと考えました。
-では最後に、DVD化にあたって、改めて映画の見どころをお話し下さい。
せりふが聞き取れなかったという人は、止めながら、じっくりと反すうしながら見てもらえればいいかなと(笑)。映画の面白さは人間を描くことですが、そこには比喩や隠喩があって、僕の好きな、黒澤(明)さん、小津(安二郎)さん、ハワード・ホークス、スタンリー・キューブリックといった監督の作品にはそれが豊富にあります。だから観客は彼らの映画を見て、自分なりの解釈がいろいろとできるわけです。実はこの『関ヶ原』にも、隠されたメッセージや、メタファーとして入れているものがたくさんあって、DVDには、そういうところを発見する喜びがあると思います。
それから、ロケ場所と人物の絡みですね。今回は本当に理想的なロケ地が全て選べたのですが、そういう所は実は全て火気厳禁なんです。だからこの作品の場合は、ロケーションが良ければ良いほど、ろうそくの火は全てCGです。全カットのうちの約半分は何らかの形でCGを使っています。そうした今の映画ならではの面白さを見付けてもらえればと思います。あとは、一人一人のエキストラの表情に見えるハリウッド映画とは違った気力とか。そういうものは、DVDで何回も見ることでしか感じられないかもしれません。いずれにせよ「この映画には、映画の面白さがいっぱい詰まっていますよ」ということです。
(取材・文・写真/田中雄二)
関連ニュースRELATED NEWS
特集・インタビューFEATURE & INTERVIEW
「栄養たっぷりないちごを食べて、元気にライブに来て」 「原因は自分にある。」大倉&吉澤が渋谷で呼びかけ
2026年2月2日
7人組ボーカルダンスグループ「原因は自分にある。」の大倉空人と吉澤要人が2月1日、東京・渋谷で開催された「とちぎのいちごふぇす2026」のトークショーに登壇した。 このイベントは、収穫量日本一の「いちご王国」栃木県産いちごの魅力を味わっ … 続きを読む
「リブート」「もうみんながリブートしていそうな気がする」「シュークリームが食べたくなる」
ドラマ2026年2月2日
日曜劇場「リブート」(TBS系)の第3話が、1日に放送された。 本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪 … 続きを読む
「パンダより恋が苦手な私たち」「椎堂先生(生田斗真)ってモデルさんだったの?」「動物の求愛行動から恋愛を学ぶって、雑学としても面白い」
ドラマ2026年2月2日
「パンダより恋が苦手な私たち」(日テレ系)の第4話が、31日に放送された。 本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ! 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。(* … 続きを読む
「DREAM STAGE」“吾妻”中村倫也のせりふに「心を打たれた」 「寝起きの吾妻PDの破壊力がすごい」「闇鍋には笑った」
ドラマ2026年2月1日
中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」(TBS系)の第3話が、30日に放送された。(※以下、ネタバレを含みます) 本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤(中村)が、落ちこぼれボーイズグループ「 … 続きを読む
小南満佑子、ミュージカル初主演に意気込み「身に余るほどの大きな挑戦になる」 ミュージカル「レイディ・ベス」【インタビュー】
舞台・ミュージカル2026年1月31日
約45年の長きにわたり英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描き出すミュージカル「レイディ・ベス」が2月9日(月)から上演される。タイトルロールとなるレイディ・ベスをダブルキャストで演じるのは、奥田いろは(乃木坂4 … 続きを読む