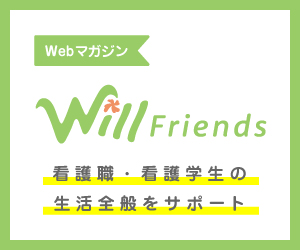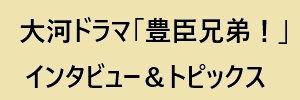エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
小泉堯史監督、松坂桃李「この話は、今だからこそちゃんと残す意義があると思いました」『雪の花 -ともに在りて-』【インタビュー】
江戸時代末期の福井藩を舞台に、数年ごとに大流行して多くの人命を奪う疫病から人々を救うために奔走した実在の町医者・笠原良策の姿を描いた『雪の花 -ともに在りて-』が1月24日から全国公開される。本作の小泉堯史監督と主人公の笠原良策を演じた松坂桃李に話を聞いた。

(左から)松坂桃李、小泉堯史監督 (C)エンタメOVO
-監督、今なぜこの映画を撮ろうと思ったのでしょうか。
小泉 吉村昭さんの原作にひかれ、映画にしたいと思いました。僕の今までの映画がそうなのですが、人物にひかれることが多いんです。その人に出会ってみたいという思いが強くありますね。小説から具象的にスクリーンに立ち上げてみたいというか、映画を作ることによって、その人物をもっとよく知ることができるのではと。そういう魅力ある人でなければ撮る気がしないですね。愛情が持てる人であれば、スタッフと一緒になって、その人物のことをもっと深く知っていくことができますから。
-この映画はウイルス(天然痘)を扱った話ですから、当然、コロナのことも意識したと思いますが。
小泉 コロナのことはプロデューサー的に、「これは」というのはあったと思います。僕は撮影が終わっても公開までなかなか次に進めないんです。でも、コロナで3年も4年も空いたので、プロデューサーも心配して、いくつか企画を提示してくれましたが、それはどうも合わなくて。それで、「吉村さんの『雪の花』だったらどうですか」という話をしたら、ぜひそれをと。コロナを意識していないわけではありませんが、歴史と伝統を大切に、医者として病に対峙(たいじ)し、いかに生きるか。その生き方を問う作品ではありますね。
-松坂さんは最初に脚本を読んだ時にどう思いましたか。
松坂 今の時代だからこそ、監督もこの映画を作ろうと考えたのかなと思いました。すごく今と通じるものを感じましたし、疫病がまん延してきた時に隔離する様子もコロナと重なりました。やっていることが今も昔も変わらなくて、すごく身近に感じました。だからこの話は、今だからこそちゃんと残す意義があると思いました。
-良策役に松坂さんというのは、初めから監督のイメージとしてあったのですか。
小泉 脚本を書き始めると、人物が自分の中で動き出しますよね。そうすると「この人物を誰にお願いすればいいか」と想像し始めます。今回は書きながら松坂さんの姿が浮かんできました。
-松坂さんは実際に演じてみて良策のキャラクターをどう捉えましたか。
松坂 疫病が広まったことによって、漢方医だった良策さんが改めて一から蘭方を学び直すというのは、すごく大変なことだったと思います。それは、漢方医としてのプライドもある中で、新しいものを取り入れて、多くの人たちの命を救いたいと思ったからです。無名の町医者ということで、風当たりがすごく強かったにもかかわらず、献身的な妻・千穂(芳根京子)の支えや、役所(広司)さんが演じる日野鼎哉(ていさい)先生をはじめ、多くの人たちの手を借りながら、自分の足を使って、多くの人たちの命を助けるという偉業を成し遂げた。良策さんの医者としての志の強さみたいなものをすごく感じました。
-演じる上で、心掛けたことや気を付けたことはありましたか。
松坂 監督から「本番までに本読みやリハーサルを重ねてきたので、あとはもう素直に演じてもらえればいい」という言葉を頂いたので、それを頼りに演じさせていただきました。本番までにやれるだけのことはやったということです。あとは相手のせりふをきちんと聞いて、その場に立った時に目に入ってくる情報や、相手の表情などもちゃんと受け入れられるようにリラックスした状態で臨むことで、ようやく素直に演じることができるのかなと思いました。
関連ニュースRELATED NEWS
特集・インタビューFEATURE & INTERVIEW
【物語りの遺伝子 “忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー】(12)道明寺天満宮と歴史の英雄たち ~野見宿禰、白太夫、そして道真~
舞台・ミュージカル2026年2月19日
YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった——。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎(たまだ・ぎょくしゅうさい)が、知られざる一門の歴史物語をたどります。 ▼相撲 … 続きを読む
小林聡美、名作ドラマ「岸辺のアルバム」 舞台化は「今の時代も共感できる」【インタビュー】
舞台・ミュージカル2026年2月19日
小林聡美が主演する舞台「岸辺のアルバム」が、4月3日から上演される。本作は、数々の名作ドラマを世に残した山田太一が原作・脚本を務め、1977年に放送された連続ドラマを舞台化。一見平和で平凡な中流家庭の崩壊と再生を描く。ドラマでは八千草薫が … 続きを読む
「豊臣兄弟!」第6回「兄弟の絆」 序盤の集大成となった小一郎必死の説得【大河ドラマコラム】
ドラマ2026年2月17日
NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟!」。戦国時代、主人公・豊臣秀長(=小一郎/仲野太賀)が、兄・秀吉(=藤吉郎/池松壮亮)を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。2月15日に放送された第6回「兄弟の絆」 … 続きを読む
名取裕子「“ぜひ友近さんと”とお願いして」友近「名取さんとコンビでやっていきたい」2時間サスペンスを愛する2人が念願のW主演『テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル』【インタビュー】
映画2026年2月16日
「法医学教室の事件ファイル」シリーズを始め、数多くの2時間サスペンスで活躍してきた名取裕子。そして、2時間サスペンスを愛する人気お笑い芸人の友近。プライベートでも親交のある2人が、“2時間サスペンス“の世界観を復活させた『2時間サスペンス … 続きを読む
ゆりやんレトリィバァ監督、南沙良「この映画を見た後で告白されたらもう振ることはできないと思います。だから“恋愛成就ムービー”なんです」『禍禍女』【インタビュー】
映画2026年2月14日
お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが映画監督に初挑戦した『禍禍女』が絶賛上映中だ。「好きになられたら終わり」という「禍禍女」を題材に、ゆりやん自身のこれまでの恋愛を投影しながら描いたホラー映画。ゆりやん監督と早苗役で主演した南沙良に話を聞い … 続きを読む