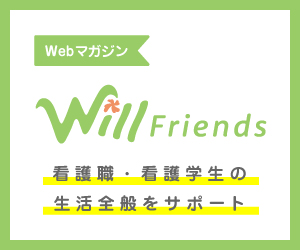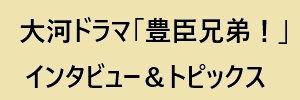エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
光石研、大倉孝二「ちょっと重いけれどちゃんとエンターテインメントになっていると思います」『でっちあげ ~殺人教師と呼ばれた男』【インタビュー】
-三池崇史監督の演出や映画に対する姿勢についてはどう感じましたか。
大倉 あまり無駄なことはおっしゃらないです。すごく明確な演出をなさいます。僕の場合は、校長と薮下先生との間に挟まれているという、スタンスにちょっとよどみがあったのかもしれなくて。監督から「きっぱりと、もっとはっきりと校長のように責め立てるようにしてほしい」と言われました。だから中途半端なことをしても駄目だと思いました。
光石 三池組は、キャスティングをした時点でもう設計ができています。あとは俳優がどういうもの持ってくるのかを見て、微調整をしてくださる感じです。だから、とてもやりやすいです。ただ、今回はスタッフの皆さんもいつも以上に真剣に、かなり熱を入れてやっていましたから、現場は厳かな感じでした。三池監督とは久しぶりでしたけど、年齢が近いからいろいろと分かってくださっているという安心感があるような気がします。
-今回、お互いの演技を見て、あるいはやり取りをしながら、お互いのことをどう思いましたか。
大倉 光石さんは大先輩ですから、僕はずっと緊張していました。
光石 僕は大倉さんの舞台もドラマもよく拝見していて、本当にうまいなと思っていました。ドラマでご一緒したことは何度かありましたが、こんなにコンビみたいなのは初めてだったので、「2、3本違うところでやってからのこの作品だったら僕たちもっとできたよね」みたいな思いがあります。やっぱり、僕自身はちょっと遠慮するところもあったので、それが反省点ではありますが、とても楽しかったです。やっぱりさすがでした。
大倉 いやもう、僕は本当に緊張しましたけど、ご一緒できたのはとてもうれしかったです。もう大尊敬しています。あまり言うと変な感じになりますが…(笑)。
-改めてじっくりと共演してみたいと思いましたか。
光石 もちろんです! 何だったら本当にコンビを組んでやりたいですね。ほんとにお上手な方だから、一緒にやっていて楽しいんです。多分こっちがどうやっても受けてくださるだろうという頼もしさもあるので、何度でもご一緒したいです。
大倉 三池さんも含めて、その世代の人たちが映画を撮っている現場に一緒にいられるだけでもすごい幸福感がありました。もう本当にうれしかったですし、ぜひまたこういう場に自分もいたいなと思いました。
-完成作を見た印象をお願いします。
光石 何か後味が悪いというか、苦しいですけど、やっぱりちゃんとエンターテインメントになっていて面白かったなと思いました。
大倉 本当につらい。ろくなやつが出てこない話ですからね。でも最後の最後に、そんな中にでもちょっとした光はあるというところで、何ごともそうなるといいなと思いました。
-これから映画を見る人たちに向けて見どころも含めて一言お願いします。
光石 この映画に出てくる人たちも普通に生活している人たちです。だから、見ている人もこのキャラクターの誰かになり得るという恐ろしさがある。友達と見に行って、こんなことがあったら怖いねとか、あの立場になったらどうするといった話もできます。ちょっと重いけれどちゃんとエンターテインメントになっていると思います。だから、いろんな世代の人に見てもらえると思います。
大倉 決して愉快な気持ちになれる映画ではないですけど、見る意義はあると思います。保身をする人間ばかりが出てくる中で、自分ならどうするかと思いながら見ていただけたらと。映画にそういうメッセージ性があるのは、いいことだと思います。
(取材・文・写真/田中雄二)

(C)2007 福田ますみ/新潮社 (C)2025「でっちあげ」製作委員会
関連ニュースRELATED NEWS
特集・インタビューFEATURE & INTERVIEW
「栄養たっぷりないちごを食べて、元気にライブに来て」 「原因は自分にある。」大倉&吉澤が渋谷で呼びかけ
2026年2月2日
7人組ボーカルダンスグループ「原因は自分にある。」の大倉空人と吉澤要人が2月1日、東京・渋谷で開催された「とちぎのいちごふぇす2026」のトークショーに登壇した。 このイベントは、収穫量日本一の「いちご王国」栃木県産いちごの魅力を味わっ … 続きを読む
「リブート」「もうみんながリブートしていそうな気がする」「シュークリームが食べたくなる」
ドラマ2026年2月2日
日曜劇場「リブート」(TBS系)の第3話が、1日に放送された。 本作は、最愛の妻の死をめぐってうそと真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒濤のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。鈴木亮平が善良なパティシエと悪 … 続きを読む
「パンダより恋が苦手な私たち」「椎堂先生(生田斗真)ってモデルさんだったの?」「動物の求愛行動から恋愛を学ぶって、雑学としても面白い」
ドラマ2026年2月2日
「パンダより恋が苦手な私たち」(日テレ系)の第4話が、31日に放送された。 本作は、仕事に恋に人間関係…解決したいなら“野生”に学べ! 前代未聞、動物の求愛行動から幸せに生きるためのヒントを学ぶ新感覚のアカデミック・ラブコメディー。(* … 続きを読む
「DREAM STAGE」“吾妻”中村倫也のせりふに「心を打たれた」 「寝起きの吾妻PDの破壊力がすごい」「闇鍋には笑った」
ドラマ2026年2月1日
中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」(TBS系)の第3話が、30日に放送された。(※以下、ネタバレを含みます) 本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤(中村)が、落ちこぼれボーイズグループ「 … 続きを読む
小南満佑子、ミュージカル初主演に意気込み「身に余るほどの大きな挑戦になる」 ミュージカル「レイディ・ベス」【インタビュー】
舞台・ミュージカル2026年1月31日
約45年の長きにわたり英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描き出すミュージカル「レイディ・ベス」が2月9日(月)から上演される。タイトルロールとなるレイディ・ベスをダブルキャストで演じるのは、奥田いろは(乃木坂4 … 続きを読む