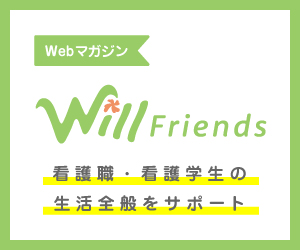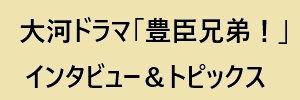エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
【インタビュー】ダンスカンパニーDAZZLE・長谷川達也 「生で見ることで、五感を刺激され、感情が豊かになっていく」
昨今の舞台・演劇業界では、観客がその世界観を存分に体感できる演出を施した“体験型”とも呼べる作品が数多く見られる。その最たる公演形態である、本格的なイマーシブシアター(没入型演劇)を日本で初めて公演するなど、新たな表現の可能性を提示し続けているダンスカンパニーがある。ストリートダンスとコンテンポラリーダンスを融合させた、唯一無二のスタイルで見るものを魅了するDAZZLEだ。彼らの公演はダンスという枠を超え、観客が共に感じ、共に考え、共に楽しめるエンターテインメント作品だ。今回は、DAZZLを主宰する長谷川達也に、作品制作への思いを聞いた。
-DAZZLEの舞台作品は、映像によるテキストやナレーションで物語性の強い作品を上演しています。それはダンスカンパニーとしては非常に珍しいことだと思いますが、どんな思いから現在の作風になったのですか。
もともとDAZZLEは「ストリートダンスの世界で活躍したい」という思いを持って活動を始めたわけですが、活動を続ける中で、そこで抜きん出るためには独自性が大事だと感じるようになりました。それで、音楽にファッション、空間の演出や人物の構成や配置といった、さまざまな要素を駆使した舞台表現で見せていこうと考えたんです。その一つ一つの要素を、どうこだわり、どう組み合わせていくかに、自分たちらしさを見つけていくことで、独自性を出すことができる、と。
-なるほど。
それから、一般的にストリートダンスはダンサーに向けて見せるためのステージが多いのですが、僕たちはアーティストとして生きていくためにも、ダンスを知らない人が見ても面白いと思える表現をしていかなければならないとも考えました。そこから生まれたのが、「物語」を取り入れるという発想です。実は、これはストリートダンスシーンでは、とても異色なことでした。ストリートダンスの多くは、いわゆる自己表現のためにあるものだったので、自分じゃない何者かになって表現するということはほとんどないことだったんです。僕は子どもの頃から映画やゲーム、漫画が大好きで、それらに共通するものが「物語」だったことからも、「物語を読む、聞く」ことは誰にでも自然に浸み込むものだと思っていたので、ダンスで物語を表現することをやってみようと思ったのがきっかけでした。
-DAZZLEの公演ではマルチエンディングやマルチストーリーなど、ストーリーが分岐していく作品も数多く見られます。
2016年の「鱗人輪舞」という作品では、二つのエンディングを用意し、観客の皆さんに、公演の途中で投票してもらい、公演の結末が変わる、という手法で上演しました。演者としては、プレッシャーもありましたが、それ以上に手応えも感じていましたし、投票結果が日に日に変化していくことに、人間の心理が反映されているようで面白かったです。
-そして、17年からはイマーシブシアターを上演しています。イマーシブシアターとは、どういったものですか。
イマーシブシアターとは、劇場ではなく施設全体を使って、同時多発的にパフォーマンスを行うものです。2019年には「SHELTER」という作品を上演しましたが、それはDAZZLEの9人全員が、開演から終演まで、それぞれのキャラクターを演じ続けるということを同時に行いました。そして、そのパフォーマンスを見た観客の皆さんが、エンディングを選びます。「SHELTER」では、30種類以上のエンディングを用意していました。
-イマーシブシアターを上演しようと思ったきっかけは?
DAZZLEのメンバーがニューヨークで「スリープノーモア」という作品を見て、自分たちもやりたい、という提案は以前からしてくれていたんです。話を聞いただけでは上演するのは難しいと思ったのですが、実際に僕もニューヨークまで行って見てみたら、「ああ、こういうことか」、と。そして、作品を体験してみて、DAZZLEがイマーシブシアターをやったら、より緻密で、より面白い作品ができるんじゃないかと思って、すぐに制作にとりかかりました。
-より緻密に作れるというのは、例えばどういった部分で?
「スリープノーモア」という作品は、入場してから退場するまで完全に自由なんです。どこを見てもいいし、どこを見なくてもいい。でも、日本で上演するに当たっては、その自由さはむしろ不自由になると感じたんです。「どうぞ、ご自由に」と言われても、どうしていいか分からない人の方が多い。そこで、僕たちの公演では、人の流れを計算して、見てもらいたいシーンを必ず見せることで、物語の軸や物語の導入部分を全員に体験してもらい、より没入感を高めたいと思いました。そういった流れの作り方とシーンの数、そして各部屋の振り付け、出演人数から音楽の流れまで、全てにおいて止まることなく動かすための、緻密な計算をして制作しています。
-消極的なところがある日本人には向いていない公演形態のようにも思えますが、実際に上演してどう感じましたか。
確かに最初は戸惑いを感じた観客もいたかもしれませんが、始まってすぐにそれは解消されました。それは、物語の導入部分はきちんと案内して、見ていただいたということが大きかったと思います。それから、なるべく伝わりやすいように言葉を使った説明も入れていたので、それを聞いてくだされば理解できる作りにはしていました。ただ、イマーシブシアターというものは1回では全部を見ることができない作りになっているので、物足りなさを感じる方はいらっしゃったかもしれません。その後に、リピートしてくださるお客さまが多かったと思います。
特集・インタビューFEATURE & INTERVIEW
【物語りの遺伝子 “忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー】(11)道明寺天満宮と歴史の英雄たち~正成、幸村、そして道真〜
舞台・ミュージカル2026年1月29日
YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった——。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎(たまだ・ぎょくしゅうさい)が、知られざる一門の歴史物語をたどります。 神道講釈師は、人々が日々の生活で … 続きを読む
「未来のムスコ」「親子って産んで終わりじゃなくてそこからのプロセスで本当の親子になるんだね」「まー先生(小瀧望)現実の保育園にもいてほしい」
ドラマ2026年1月28日
火曜ドラマ「未来のムスコ」の(TBS系)の第3話が、27日に放送された。 本作は、夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来(志田未来)のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る颯太(天野優)が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。 … 続きを読む
「再会」“南良刑事”江口のりこの怪演が面白い 「取り調べが怖過ぎる」「コナン以上にキレッキレ」
ドラマ2026年1月28日
竹内涼真が主演するドラマ「再会~Silent Truth~」(テレビ朝日系)の第3話が、27日に放送された。(※以下、ネタバレを含みます) 本作は、横関大氏の推理小説『再会』をドラマ化。刑事・飛奈淳一(竹内)が、殺人事件の容疑者となった … 続きを読む
坂本昌行&松崎祐介が「るつぼ The Crucible」で舞台初共演 「人間味のあるリアルな感情を表現できたら」【インタビュー】
舞台・ミュージカル2026年1月28日
坂本昌行が主演する舞台「るつぼ The Crucible」が3月14日から東京芸術劇場プレイハウスで上演される。本作は、「セールスマンの死」や「橋からの眺め」などで知られる劇作家アーサー・ミラーの代表作で、1692年にマサチューセッツ州セ … 続きを読む
「夫に間違いありません」“光聖”中村海人の苦悩に同情の声 「姉弟が不遇過ぎる」「土砂降りの車のシーンはつらかった」
ドラマ2026年1月27日
松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」(カンテレ・フジテレビ系)の第4話が、26日に放送された。(※以下、ネタバレを含みます) 本作は、主人公・朝比聖子(松下)が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還す … 続きを読む