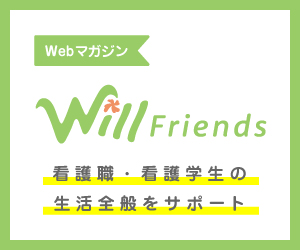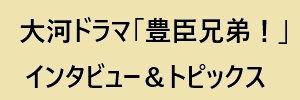エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
【物語りの遺伝子 “忍者”を広めた講談・玉田家ストーリー】(7)神々がすむ土地を語る
YouTubeもNetflixもない時代、人々を夢中にさせた“物語り”の芸があった——。“たまたま”講談界に入った四代目・玉田玉秀斎(たまだ・ぎょくしゅうさい)が、知られざる一門の歴史物語をたどります。

▼玉田永教と神道講釈
銭湯の湯けむりの中で響いた「チョコチョコ」「ヌルヌル」「ドボン」。オノマトペに満ちた日常が、講談師としての“耳”を育てました。しかし、講談の源はもっと深く、もっと古いところにあったのです。それは、神々の物語を語り伝えた芸の系譜でした。
玉田家の始まりは、江戸後期に神道講釈師として活躍した玉田永教(たまだ・ながのり/えいきょう)というお方です。
“神道講釈”とは、今では耳慣れぬ言葉ですが、「そこで住んでよかった」、「生活してよかった」――そんな思いを呼び起こす、その土地の物語を語り、その地に生きる意味を伝える芸でございました。
この神道講釈の学問的研究は今も続いているので、ご興味のある方はぜひ一度お調べいただきたい。きっと、まだ知らぬ日本の歴史に出会えることでしょう。
さて、私の師匠、四代目旭堂南陵(きょくどう・なんりょう)も、神道講釈の復活に心血を注いでおりました。
2016年に私が四代目玉田玉秀斎を襲名しました背景にも、「神道講釈、そしてヒーロー忍者の玉田家を復活させねば、上方講談の再興はない」という師匠の信念がございました。
南陵が復活させた神道講釈には、『安倍晴明伝』と『菅原道真天神記』があります。なかでも『安倍晴明伝』は圧巻で、神職の白衣に烏帽子、笏(しゃく)を手に、高座の四方に細竹を立てて結界を張り、その中で語られたこともございました。明治期の文献にも、まさにその光景が記されております。
▼神々がすむ土地を語れ
しかし、江戸期の神道講釈は少し違うものでした。
永教の語りは、呼ばれた土地へ赴き、その地の人々の物語を即興で編み上げる、いわば“オーダーメイド講釈”でございました。
神職の資格を持ち、吉田神道の教授職でもあった永教は、各地で神道講釈を行い、多くの門弟を育て、下鴨神社の南には広大な邸宅を構えていたと伝わっております。
このように土地の物語を語る姿勢こそ、玉田家の真骨頂。招かれた土地で、その地にふさわしい物語を新たに生み出す。つまり、玉田家の講談は新作創作するのが伝統なのです。その伝統は、今の私の講談にも息づいております。私の語る物語の九割九分は新作、創作です。
日本の面白さは、神社が物語を数多く残しているところにあります。神社の数は約8万社、コンビニは約5万店といわれ、コンビニよりも便利です。
神社があるところには、必ず物語がある。なぜなら、そこにはその土地に必要とされた神々がいて、なぜその神々がそこに祀られたのか、その由来が語り継がれているからです。
物語の観点から見ると、神社こそ、その土地の数千年にわたる歴史を今に伝え、“物語を保存してきた装置”なのです。それを基に、その土地にまつわるオーダーメイド物語を創作し語っていたのが、玉田永教の神道講釈でございました。
私は今、その精神を受け継ぎ、現代に息づく新たな神道講釈を蘇らせようとしております。
そのことについては次回のお楽しみ。
■四代目・玉田玉秀斎
玉田家は幕末、京都を拠点に活躍した神道講釈師・玉田永教の流れをくみ、三代目玉秀斎は『猿飛佐助』『真田十勇士』『菅原天神記』『安倍晴明伝』などを世に広め、明治大正期の若者に大きな影響を与えた。四代目玉秀斎はロータリー交換留学生としてスウェーデンに留学中、逆に日本に興味を持ち講談師に。英語講談や音楽コラボ講談、地域に残る物語に光を当てる“観光講談”に力を入れ、ホームレス経験者への取材を元にしたビッグイシュー講談、SDGs講談など創作多数。更に文楽や吉本新喜劇、地域の伝統芸能とのコラボ公演も多い。2024年3月三重大学大学院修士課程「忍者・忍術学コース」修了。2024年4月より和歌山大学大学院・観光学研究科後期博士課程にて研究中。