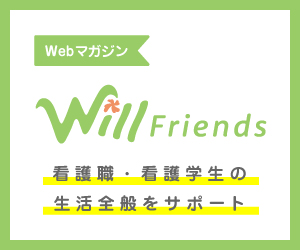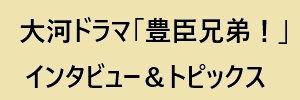エンターテインメント・ウェブマガジン
エンタメOVO(オーヴォ)
【Kカルチャーの視点】レジェンドたちの「朝鮮の旅」たどった写真家の藤本巧さん
▼生きた建築、通度寺の一本はしご
「自分で芸術作品を撮るのも大事ですが、先生方の文章に合わせて写真を撮ることに生きがいを感じます。作詞作曲のように、一つの詩があって、そこに私が曲をつけているのです。」
昔の日本もこのような美しい市が立った。人里遠い山の中から、大きな丸太のくり抜きの水がめやかまどを担いで出てきた人たち…水色やもえぎ色のチョゴリを着た女たち――「朝鮮の道」の生き生きとした描写は、藤本さんの写真によって鮮やかさを増していた。
市日に集まる白衣の人々を実際に目にしたときは、旅館の2階から夢中でシャッターを切った。柳宗悦が朝鮮の白磁を見て「これだ」と感じたように、藤本さんもまた慶尚南道の古刹(こさつ)・通度寺(トンドサ)の板倉に架けられた一本のはしごに目を奪われた。
「河井先生がインタビューテープで“生きた建築”、“欲しいくらい”と力説されていたものがまだ残っていたのです。(河井先生の描写のように)一本の丸太から手斧で削り出したようなはしごはありのままに曲がっていて見事でした。後年、粗大ごみとして捨てられたと聞いた時は、本当にガッカリしました。」

藤本巧さんの講演会で紹介された通度寺の一本はしご
だが、柳らが見た風景を追っていた藤本さんに転機が訪れる。
「1972年、釜山でお葬式を撮影したときです。喪主の息子さんがワイシャツに革靴という現代的な格好をしていました。それでシャッターをためらっていると、当時お世話になっていた昔度輪先生(韓国美術評論家)から『どうしてシャッターを切らないのか。これも現実だ。こういう写真も撮れなくてはだめだ』と諭されました。セマウル運動によって私が求めていたような風景はなくなりましたが、それ以降、新しい視野で韓国を捉えるようになりました。」